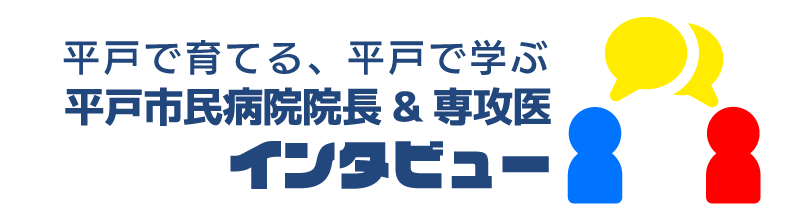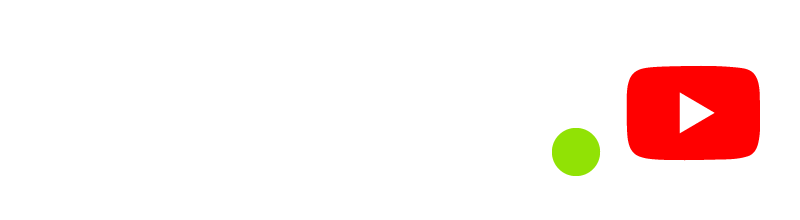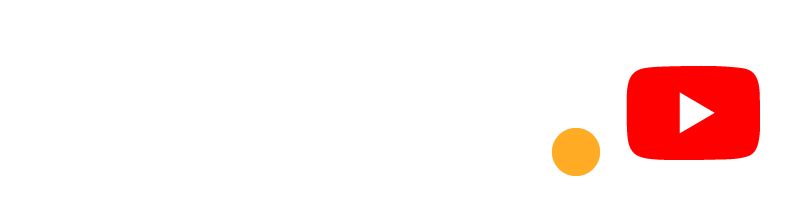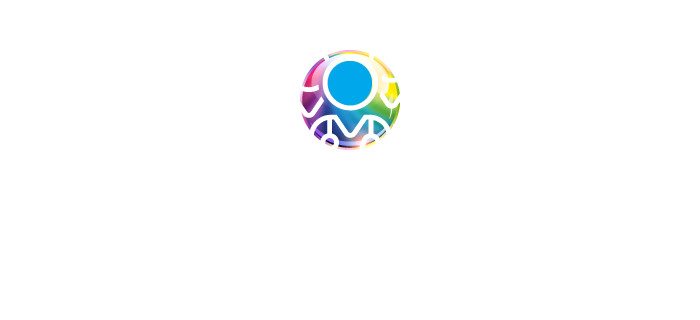経験者メッセージ
山本 杏子 (平戸市民病院)

山本 杏子
(平戸市民病院)
(平戸市民病院)
この度はご縁をいただきまして、地域医療を学びたいと令和6年5月から令和7年3月まで約1年間、平戸市民病院で勤務いたしました。神戸出身で関西以外に住んだことがなく、関西弁丸出しだった内科の山本です。大阪以外で働くのも初めてで、循環器内科・内科E R経験はありましたが、小児科や傷、骨折などはあまり経験がなく、しかし選り好みはできない全部診なければならないと、、実は赴任当初は常勤の先生方を探し、本と睨めっこしておりました。蛇咬傷やダニ関連疾患などなかなか大阪では経験できない症例も経験できました。そして何より、90歳代の患者さんが元気に一人で外来に通っている姿には驚きました。在宅医療も初めての経験でしたが、地域をよく知る上で貴重な経験でした。疾患のみでなく、交通手段や生活環境なども考慮することが大切だと改めて感じました。看護師さんを初め病院スタッフには非常に助けられました。難解地名に方言と初めはスタッフの助けなしには診療業務ができませんでした。そして、患者さんからの学びも多くありました。患者さん同士のつながりなどが助けになることも多々ありました。その上で平戸市民病院はそういった地域全体の繋がりで持って支えられているのだと感じました。また、高次医療施設まで1時間近く離れている平戸においていかに病気を早期に発見すること、予防することの重要性を痛感しました。健康診断がいかに重要か。皆さん1年に1度ぜひ受けてくださいね!血圧毎日でなくてもいいので計りましょうね!
病院以外でもしっかり平戸生活を堪能しました。志々伎のお魚祭りや酒屋さんの蔵開きや軽トラ市などしっかりイベントも楽しみました。夏は真っ黒に日焼けするほど根獅子や人津久の海で泳ぎました。秋冬はひたすら、今まで食べた魚はなんだったんだと思うほど美味しい魚や野菜を頂きました。短い期間でしたが非常に有意義な時間を過ごせたことはひとえに皆さんの優しさでした。『帰りたいおばあちゃん家』ができたような感覚です。また平戸に伺います。
また、令和7年3月末に約2週間ネパールへ海外研修に行きました。カトマンズとポカラと2都市計5ヶ所の病院を見学しました。ネパールはエベレレストと発展途上国のアジアの国というイメージでした。町はいかにもアジアといったイメージ通りで、大量の車とバイクが縦横無尽に走っており何度か轢かれそうになりました。ネパール人は少しシャイで礼儀正しく、日本人の国民性に似ている感じがしました。(そして休日がなんと土曜日!日曜日から仕事始めに一番面食らいました。) しかし医療面では非常に発展しており、若手の医者は皆普通に英語が話せる、しかも流暢!圧倒されっぱなしでした。衛生問題や貧困から、日本ではもう目にしない疾患なども未だに蔓延しています。また熱帯感染症など、今まで全く経験のない疾患もよく見るようで驚きの連続でした。非常に有意義な時間でした。今後海外での医療や辺境の地での医療に興味があるので、ますます意欲が高まる良い機会でした。
病院以外でもしっかり平戸生活を堪能しました。志々伎のお魚祭りや酒屋さんの蔵開きや軽トラ市などしっかりイベントも楽しみました。夏は真っ黒に日焼けするほど根獅子や人津久の海で泳ぎました。秋冬はひたすら、今まで食べた魚はなんだったんだと思うほど美味しい魚や野菜を頂きました。短い期間でしたが非常に有意義な時間を過ごせたことはひとえに皆さんの優しさでした。『帰りたいおばあちゃん家』ができたような感覚です。また平戸に伺います。
また、令和7年3月末に約2週間ネパールへ海外研修に行きました。カトマンズとポカラと2都市計5ヶ所の病院を見学しました。ネパールはエベレレストと発展途上国のアジアの国というイメージでした。町はいかにもアジアといったイメージ通りで、大量の車とバイクが縦横無尽に走っており何度か轢かれそうになりました。ネパール人は少しシャイで礼儀正しく、日本人の国民性に似ている感じがしました。(そして休日がなんと土曜日!日曜日から仕事始めに一番面食らいました。) しかし医療面では非常に発展しており、若手の医者は皆普通に英語が話せる、しかも流暢!圧倒されっぱなしでした。衛生問題や貧困から、日本ではもう目にしない疾患なども未だに蔓延しています。また熱帯感染症など、今まで全く経験のない疾患もよく見るようで驚きの連続でした。非常に有意義な時間でした。今後海外での医療や辺境の地での医療に興味があるので、ますます意欲が高まる良い機会でした。
池田 恵理子 (平戸市民病院)

池田 恵理子
(平戸市民病院)
(平戸市民病院)
私は幼い頃に感じた、世界中で治る病気で亡くなっている子供たちに会いに行き助けたい、という思いから、国境なき医師団に出会い、医師という職業を選びました。幸運にも医師になることができ、これまた幸運にも、東南アジアやアフリカで医療をさせていただける機会にも恵まれてきました。そのたびに思うのは、「発展途上国は世界のへき地である」ということ。いかにその独特な文化や慣習に介入し、その地域に溶け込み、地域の人々と信頼関係を築き、自分が去った後も根付くような何かを残せるか。国際協力も日本のへき地も、そういったそれぞれの地域の特性に対応できる、柔軟性が必要であることを毎回実感しています。
平戸市民病院は典型的な「地域の病院」であり、目の前の患者さんだけでなく、地域の特性を理解して地域全体を診療していくという姿勢が自然に身に付く環境であると感じます。もちろん疾患も多岐にわたり、専門の枠にとらわれない対応が常に求められます。私も海外での診療を経て、自分に足りない総合診療的能力と地域医療の勉強が必要だと痛感し、平戸市民病院を希望しました。現状、期待した通りの毎日を過ごすことができており、何より上司や職員さんたちが非常に暖かく、国際協力に理解を示して下さっていることをとてもありがたく感じています。このような職場を探し求めている方は、ぜひ一度お問い合わせいただけると嬉しいです。
平戸市民病院は典型的な「地域の病院」であり、目の前の患者さんだけでなく、地域の特性を理解して地域全体を診療していくという姿勢が自然に身に付く環境であると感じます。もちろん疾患も多岐にわたり、専門の枠にとらわれない対応が常に求められます。私も海外での診療を経て、自分に足りない総合診療的能力と地域医療の勉強が必要だと痛感し、平戸市民病院を希望しました。現状、期待した通りの毎日を過ごすことができており、何より上司や職員さんたちが非常に暖かく、国際協力に理解を示して下さっていることをとてもありがたく感じています。このような職場を探し求めている方は、ぜひ一度お問い合わせいただけると嬉しいです。